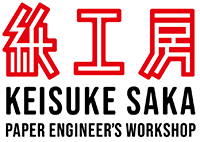パラパラめくる生命誌・その2
細胞社会のはじまり

前回のパラパラで20億年かけて進化した単細胞生物は、今から約10億年前に何かの拍子に集まり、集団内でそれぞれの細胞が自分に割り振られた役割を果たす細胞社会を作りはじめました。これが更に進化して、現在の動物や植物、菌類といった、僕らにおなじみの多細胞生物となるわけです。その進化の過程はまだ充分に解明されていないそうですが、単細胞生物と多細胞生物の間をつなぐと考えられている生物の一つが、今回取り上げた細胞性粘菌「キイロタマホコリカビ」です。
普段は単細胞生物として活動しているこの粘菌、周囲のエサを食べ尽くすと同じ遺伝子型を持った細胞が寄り集まって、まるでナメクジのような形をした〈移動体〉を作り、光に向かって移動を始めます。肉眼でも確認できるその姿はまるで動物のようなんですが、この〈移動体〉には筋肉細胞や神経細胞といった役割分担はありません。まったく同じ細胞が数千から数十万個も集まっているだけなのです。光のあたる所まで来た移動体は動きを止めて胞子の塊を高く持ち上げて〈子実体〉となり、ネバネバした胞子が昆虫の脚などに付いて移動して次代の粘菌となるわけなんですが、面白いのが胞子塊を持ち上げる〈柄〉になる部分。この〈柄〉の役割を担った細胞は、自分の遺伝子を残すことができず、そのまま死に絶えてしまいます。気の毒な〈柄〉になるか、将来有望な〈胞子〉になるかは、アメーバ状の単細胞が集合する際に〈移動体〉の中でどのポジションを占めるかによって決まるそうで、つまりは同じ細胞同士の間で知らぬ間に役割分担がなされているわけですね。これが現在の多細胞生物に見られる、器官ごとの細胞の形や機能の違いのハシリなんじゃないかというのが、今回のおまけのテーマになります。実験的に、異なる遺伝子型を持つ粘菌を混ぜ合わせてみると、将来〈柄〉になる〈移動体〉の先端の部分にはなかなか細胞が集まらず、結果的に〈柄〉が短い〈子実体〉になるそうで、まるで自分の将来を予期しているかのような単細胞生物の振る舞いは何とも不思議です。